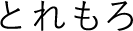はいくふぃくしょん中嶋憲武による掌編小説
末裔
する事はこれと言って無い。小さな川に沿ってぶらぶらと歩く。薄日の差し込む川面は、どんよりと重く鈍い煌きを放ちながら、ゆっくりと流れていた。川の流れの先にスカイツリーが見える。虚無的な男の一瞥のようにくらりくらりと灯を廻している。鉄柵に凭れ暗い水のゆくえを眺めていると、視界の端を白いものが翻ったような気がした。まさかと思って見上げると、やはり鶴だった。鶴は仕舞屋の陰に隠れて見えなくなった。俺は再び川に目をやった。
夕食はどうするか。豆腐でも食うかと考えた時、背後に気配がして「もし」と声を掛けられたので、振り向くと妙齢の女が立っていた。ほっそりとした体を柔らかそうなカシミヤの白いコートに包み、大きな黒い瞳が恬淡と俺を見た。余りに恋愛と縁遠い生活を送っている俺は、これは好機が訪れたのかもしれないぞ、そうだ、間違いなく恋だと考えた。俺は顔だってまあまあだと思っている。自信を持って誘ってみろと自分を鼓舞した。だがその必要は無かった。女は、どこかでお茶が飲みたいと言ったのだ。
しばらく歩くと「王城」という喫茶店があったので、そこへ入った。コートを脱いで、白いタートルネックのセーター姿になった女は、思っていたよりも豊満な胸をしていた。女はロシアン・ティーを頼み、俺はブラジルを頼んだ。ほくほくと女を見ると、「昔はよくこの辺にも飛んで来てました」と言った。俺は女が何を言っているのか分からなかったので、よくよく聞いてみると、女は鶴なのだと言う。そう言われれば、そんな気もしてくるのだった。「鶴って、やっぱ長生きなの?」何を聞いているんだ俺は、と思ったが女は真面目だった。二百七十年生きているが、まだまだ若い方なのだそうだ。私の祖父は千五百年生きましたと付け加えた。広重の絵に描かれているのは祖父と兄です。兄は悲しい最期を遂げました。女はさめざめと泣いた。
どんな縁でも女に泣かれるのは気まずい。気まずい雰囲気のまま、店を出て堤防に沿って歩いた。宝暦二年の冬に、と女は切り出した。鷹狩があって兄は捕まりました。鷹匠が兄の肝を抜き、塩を詰めました。都へ献上するためです。翌日の朝、檜の立派な輿に羽を広げた姿で兄は載せられ、都へ旅立って行きました。上様は微笑してご覧になっていました。鷹匠も傍に仕えていました。あなたはその鷹匠の末裔なのです。そう言って女は堤防を降りて行き、橋桁の陰へ入った。わたしの合図があるまで目をつぶっていてください。もしも途中で目を開けると、あなたは死にますと言った。目を瞑ると洋服を脱いでいる気配がしたので、目を開けてみたかったが我慢した。やがて女がいいですと言ったので目を開けると、一羽の美しい鶴が立っていた。あなたを見ておきたかったのですと言って、大きく二三回羽搏くと北へ向かって飛び立った。俺は鶴が見えなくなるまで北の空を見ていた。
鶴つつむ古い布あまねく朝日 田島健一 (2013年4月号梨花集より)
炎環 2013年7月号より転載