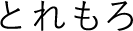はいくふぃくしょん中嶋憲武による掌編小説
限界と終局
どれぐらい経ったのだろう。仕事で近くまで来たので、懐かしくなって寄ってみたが、あの頃と同じ様子で建っている。木造モルタ造りの二階建て。破風の白いところに「あけぼの荘」と墨文字で太々と書かれてある。
ブロック塀が周囲を囲い、入り口は両脇が角柱になっていて、丸い門灯がそれぞれに鎮座している。辺りがうす青い闇に変じて来ると、橙色の明りがぽっと灯る。きゅるきゅると軋む引戸を開けると広めの玄関で、下駄箱へ運動靴(あの頃はスニーカーなんて言わなかった)を仕舞い、階段を上がって廊下を少し歩いたところの角の六畳間が、わたしのアジールだった。
合鍵を鍵穴に差し込んで左へネジのように数回廻して戸を引き開け、この戸は開く時、ぎゅるぎゅると神経に障るような音を立てた。部屋へ入るとすぐに流しと一口コンロがあり、右側の障子を開ける六畳の城。トイレは共同で風呂無し。わたしは達はもっぱら銭湯へ行った。
絵描きの彼の部屋へ、わたしは転がり込んでいた。書物、スケッチブック、イーゼル、カンヴァス、油絵の道具。そんな物が部屋を占領していて、居場所は二畳くらいのスペースしかなかった。装飾品と言えば、映画雑誌から切り抜いたらしいジーナ・ロロブリジーダのモノクロ写真が画鋲で留めてあるだけ。彼は看板描きのアルバイトからまだ帰って来ていなかった。
食べる物が無くて新聞紙食ったよ。彼は言って笑った事もあった。絵が少々売れるようになっていた彼は、過去の悲惨をファルスにしてしまえる心の余裕を持っていた。毎日が不安に押し潰されそうだったはたちのわたしには、その余裕がとても羨ましく映った。
わたしはストーブの上に薬缶を置いて彼の帰りを待つ。カンヴァスに彼が描き散らした様々な色彩に囲まれて、オーネット・コールマンを低く流す。読みかけのホイジンガを開く。薬缶がしゅんしゅんと白い息を吐き始める頃、彼が帰ってくる。わたしのかけがえの無い時間が、そこには確かにあった。
頭蓋にオーネット・コールマンが小さく響めいていた。わたしはあけぼの荘の前に佇んでいた。よく見るとあちこち相当傷んでいる。窓ガラスが割れて、そのままになっている部屋もある。青い闇が周囲を満たしても、壊れているのか門灯の点く気配は無い。軋む戸が開いて、内側の暗闇からペルー人と思しき男が一人出て来た。胡乱な一瞥をくれて、出掛けていった。
オーネット・コールマンはだんだん大きくなって、アルト・サックスが最早半狂乱の頂点へ螺旋を伸ばして行った。あけぼの荘の壁が剝がれ出し、めきめきと罅割れたかと思うと、生木の避ける音が轟き、ガラスが飛び散り、瓦が吹っ飛び、土煙を上げて建物は崩壊した。
わたしはふと会社へ戻らなければと思った。うすら寒い銀白色の外灯が灯り、陰気なオルゴールの流れる商店街を、駅に向かって歩いて行った。
寒オリオンあけぼの荘の灯のふたつ 岸ゆうこ (2013年3月号梨花集より)
炎環 2013年6月号より転載