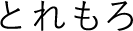はいくふぃくしょん中嶋憲武による掌編小説
古い歌
珍しくフウカが付いて来ると言うので、一緒に出る事にした。私はジューダス・プリーストの黒い野球帽に、黒いTシャツにジーパン、赤のブロックチェックのすこしくたびれた綿シャツを羽織った。今はジーパンとは言わないのだそうで、ジーパンと言うとフウカは笑ってデニムでしょうと言う。ジーパンじゃないと、何だか感じが出ないので困るのだ。
「何処へ行くの」
「その辺ぶらぶらするだけさ」
「なんだ散歩か」フウカはヘビメタが好きで、誕生日にジューダス・ブリーストの帽子をプレゼントしてくれたのだ。私は昭和十三年生まれの七十四歳。フウカは六十歳年下の十四歳。孫だ。嫁の咲子とは気が合わないが、フウカとは妙にウマが合う。
フウカを連れて歩いていると、振り返ってゆく輩がある。フウカの黒革のショートパンツ姿に興味があるのか、私達の関係に興味があるのか、聊か業腹である。フウカはそんな事、柳に風と言ったものか、素知らぬ顔してスマホで音楽を聴いている。多分、例のがちゃがちゃ節操の無い毛唐の歌舞音曲、と言ってしまえばにべも無いが、私も一時期毛唐の歌舞音曲に憧れ、自ら演奏していた事もある。「君嶋征一郎とノーザンクライマーズ」と言うロカビリーバンドを組んで、新宿や池袋のジャズ喫茶に出ていたのだ。カントリーやロカビリーの平和な時代。そのうちにビートルズが出て来て、あっという間にグルーブサウンズの時代になって、つまらない世の中になった。昭和十五年生まれのジョン・レノンが我々を置いてけぼりにしたのだ。
「セイイチロー、なんか食べたいよう」フウカは私を呼び捨てにする。
アーケードの商店街は連休でも関係無いのか、半数の店はシャッターを閉じている。我々はドーナツ屋に入った。有線でヘレン・シャピロが掛かっていた。それもお気に入りの「リトル・ミス・ロンリー」だ。私は途端に機嫌が良くなって来た。
「幾つでもお代わりしていいよ」
「そんなに食べたら太っちゃうっての」フウカはメロンソーダを頬をへこませて飲んだ。ちっちゃい頃と変わっていない。曲はレスリー・ゴーアの「イッツ・マイ・パーティ」になり、私は片足でリズムを取った。
「ノッてるね。この曲知ってるう」
「レスリー・ゴーアはビートルズを連れてツアーした事あるんだよ」
「ここのポイントカード、もうすぐ終了なんだね。」
「レスリー・ゴーアはビートルズを連れてツアーした事あるんだよ」
「聞いてるよ。セイイチロー、時々子供っぽいね」私はだだコーヒーを飲んだ。ガラスに白髪の疲れた男がいた。白髪の向こう側で公園の葉桜がそよいでいた。曲がロネッツの「ビー・マイ・ベイビー」になった。この曲をダンパで一緒に踊った娘は、パリへ行くと言ってたっけ。
葉ざくらやどこへ行くにも野球帽 細川和子 (2013年7月号梨花集より)
炎環 2013年10月号より転載