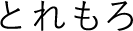はいくふぃくしょん中嶋憲武による掌編小説
ドッカツ
祖母の葬儀が済んだ。火葬場から帰ってきて、みんなは叔母の家へ行っている。わたしは、あとから東京へ帰るだけで取り立ててすることもない。叔母に、あとで寄るからと言って喪服のまま裏山へ登ってみることにした。するとネクタイを解いていた従弟の正太が「俺も」と言って、ついて来た。正太に会ったのは、三年ぶりだ。三年前、祖父の葬儀のとき会ったきりだった。親戚が集まるのは、葬式か結婚式ぐらいだ。まあ圧倒的に葬式の方が多いだろう。
叔母に会うたび、ヨリコちゃんはいつ結婚するのと聞かれる。わたしはその都度、いいひとがいたらねと答える。いいひとは、なかなか現れない。叔母は、もうすぐ三十でしょ。すぐに四十女よと言って脅す。そんな話をすると、正太はおなかを揺すって笑う。正太のおなかは見事なものだ。むかしはこうじゃなかったんだけどな。
「なんだっけなあ」と正太が呟く。
「なんだっけって、なにが?」
「と言っても、もうすぐ四十朗ですがってセリフがあんだよ。むかしの白黒映画に」わたしは気のなさそうに、へえと言ってみた
「時代劇なんだよ。なんだっけなあ」と拘泥する。
まったく格好の悪いおじさんになってしまった正太だが、小さい頃わたしは正太といるとぼーっとしてしまって、一緒にいたりすると、得意気な気持ちになったものだ。小学校に上がったばかりのわたしには、中学一年生の正太がとても大人で、アイドルのような特別な存在だった。あのときの、ぼーっとした気持ちというのは、いまでも心の奥のどこかにしまってあって、それがひょっこり出てくることがある。
ヨリコちゃんと呼ばれて振り向くと、正太が二メートルほど後ろに立って、「これ、なんだか知ってる?」と、ある植物を指差した。それは群がり繁る草の間から、にょっきり伸びていた。花火みたいだと思った。四方八方に伸びた茎の先に、まるでブローチのような紫色の実をたくさん付けていた。いままで見たこともない植物だった。
「はじめてみた」裏山には小さい頃から何度も登っているが、こんなものが生えているのを見たことがない。
「面白いでしょ」正太が言った。
「前から生えていたっけ?」
「生えていたんじゃない」
「何て言うの?これ」
「ドッカツ。薬になるらしいよ。婆ちゃんが言ってた。」
わたしはそろそろ明日の仕事のことが気になりだしていた。帰らなければ。正太は、東京で鬱になって忍野に戻って来た。国道沿いのコンビニでアルバイトをしている。ちゃんと勤まってんのかしら。
気の早い秋の夕暮れが、富士山をほんのり桜色にしている。わたしの心もいつしかぼーっとなった。桜色の富士山を眺めて二人とも無言だった。
猪の実やいつまでも人見知り 一ノ木文子 (2012年11月号梨花集より)
炎環 2013年2月号より転載