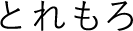はいくふぃくしょん中嶋憲武による掌編小説
靴下
「そうして我々は世界に君臨するのです」いつもながら壮大な水岡先生のお話を聞きながら、窓の外を眺める。舗道にセキレイがやって来ていて、長い尾羽をパタパタ上下に振っている。めんこいこと。何のお話をしてるんだっけ。絵画論のお話だったはずだ。それがいつのまにか、スピリチュアルな方面のお話になってしまっている。クンリン。あまり日常会話では聞きなれない言葉の響きに、わたしはくらくらしてしまって、すっかり冷めたコーヒーを一口ゆっくりと啜る。
娘が社会人になって、母親の務めがひと区切りついたので、まったく遠退いていた油絵をまたぽつぽつと描き出した。水岡先生にお会いしたのは、白鴎会という絵画制作のグループでだった。わたしたちは、アマチュアながらお互いを独立した画家として認めていたので、先生と呼び合った。月に二度あるコースに、たまにふらっとやって来て指導的な役割をしていたのが、水岡先生だった。水岡先生はわたしと同世代と思われ、もうすぐ六十に手が届こうかというのにとても若くみえた。面長の風貌に、モジャモジャの髪。白髪など一切ない。高い鷲鼻。みるからに芸術家だと思った。お描きになっている絵もとても個性的で斬新な抽象画で、どうしてこんな先生が白鴎会のようなグループに燻ぶっているのだろうと疑問に思う。
わたしは水岡先生について、あちこち出掛けるようになった。水岡先生もわたしのことを気に入ってくださったのか、たびたびお声をかけてくれて、知り合いの個展へ連れて行ってくださったり、画廊のオーナーを紹介してくださったりした。
今月は上野でル・コルビュジエをみて、鶯谷、入谷と歩いて少々くたびれたので、言問通りの裏にある小さな喫茶店でひと息入れているところだ。セキレイはもういない。お向かいの和菓子屋の黒塀に当たった強い日差の反射光をみていると、そろそろ行きますかと水岡先生。どこへ行くのか分からなけれど、はいと答えてわたしも立つ。
とぼとぼ歩いて行くと、不意に水岡先生が立ち止まり、宛ら我々は巡礼者のようですなと独りごちた。自らの芸術を求めてさまよう巡礼ですよ。例えばあそこに我々の芸術の源泉があります。ほら。といって水岡先生の指差す方をみると、築六十年は経ているだろうと思われる木造のアパートがあった。二階建てのがっしりとした造りで、木材は煤けて黒っぽい。わたしは穴蔵のようだと思った。あの窓なんかなかなかいいでしょう。靴下が一足干してあって。あれが生活です。さ、描きましょう。と水岡先生はいったかと思うと、ショルダーバッグからF4のスケッチブックを取り出し、立ったままデッサンを始めた。
夕暮のわたしたちは並んで立って、よれよれの黒い靴下の干してある窓をデッサンした。デッサンをしていると、豆柴を連れたおばあさんが通りかかり、スケッチをブックを眺めていたが、つまらないもの描いているんだねえといって、行ってしまった。生暖かい風が黒靴下を僅かに揺らした。
浅草寺裏のアパート蚯蚓鳴く 市ノ瀬遙 (2013年11月号梨花集より)
炎環 2014年2月号より転載